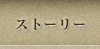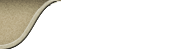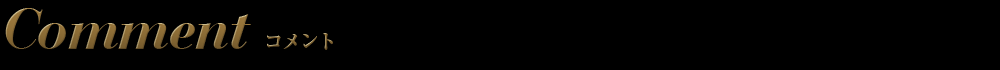
周防さんが、またまた傑作をつくった。またまたというのが凄い。
「終の信託」というタイトルは、少し説明を要するかもしれない。
「終」は死期のことである。人はいろいろだから誰でもというわけにはいかないが、多くの人は自分が終末のベッドにいて、とうとう意識もなく自力呼吸もできなくなったら、
それでも更に延命器具によって生きていたいとは思わないだろう。しかし、そうなってしまっては、この辺で死なせてくれと自分ではいえない。
これ以上の延命処置は空しいし、周囲や親族も疲れて惜別の情も薄れてしまうから、ここらで器具をはずそうという結論は本人以外の人がすることになる。
それを誰の判断に託すかを生前に決めておくのが「信託」である。「終の信託」である。
とはいえ、多くの人はそこまでのことはしていない。だから医師が親族の依託を得た上で、それを引受けることも少くないだろう。他人なら細かな感情抜きに、比較的リアルな判断ができる。
しかし、医師も完璧ではない。この作品の女性医師(草刈民代)も、私生活で悲哀をかかえ、そのせいもあって感情に傾くところがある。ある男(役所広司)の患者の、痛みや苦しみや優しさ絶望に心を寄せてしまう。
医師なら仕事の場で誰にでも公平に向き合うのが責務だが、多忙な日々しかなく、その日々の中で特別な出会いがあったとしても、誰が非難できるだろうか。ひそかな交情―といっても性愛というものではない。
いつ死期がやって来ても不思議はない男とでは、あらかじめその先へ進む道は閉ざされている。
だから二人の時間が、いわば余儀なく育てたものは、「終の信託」をあなたに託した、託されたという感情だった。それは書きものとして残されたわけではないが、
二人にとって―少くとも女性医師にとっては、たしかな心の真実だった。
男の死後、検事が登場する。
彼は心情の真実などというものは一切受けつけない。この検察庁のシークエンスは、震え上るような怖さと嫌悪感をかき立てられて、実に見事である。
その人物描写の徹底さは、ただその一検事の再現を狙うだけではなく、ある種の人間たちのシンボルとしての造形というような意志を感じた。周防さんは、もの凄くこの種の人物を嫌いなのだろう。
他者の真実を安直に判断し、人間に起きたことの本当を知ろうとせず、世界の無限定さへのひるみもなく、自信たっぷりの人たちへの軽蔑と嫌悪は、一応彼等にも理屈があると認めながら、叫び出しそうに画面から溢れてしまう。
この映画が公開されたら、「私も終の信託をしとかなくちゃあ」というように、このタイトルが日常語となって流布することを願っている。
1934年東京生まれ。
1958年松竹に入社後、1965年独立。以来、脚本家として、「男たちの旅路」シリーズ(1976年~、NHK)、「岸辺のアルバム」(1977年、TBS)、「ふぞろいの林檎たち」シリーズ(1983年~、TBS)、「ありふれた奇跡」(2009年、CX)など日本のテレビ史に残る名作ドラマを数多く発表する第一人者。『キネマの天地』(1986年、共作、山田洋次監督)、『少年時代』(1990年、篠田正浩監督)など映画や舞台の脚本も多数。小説家としても、「飛ぶ夢をしばらく見ない」、「異人たちとの夏」などの作品がある。